接着剤の特徴
接着剤とは
接着剤とは周知の通り、物と物を接着するための物質でありますが、何と何を接着するかによって数多くの種類が存在し、塗料やラミネートなどの片面を接着するという概念のものも接着剤の一種に分類されます。
接着剤の役割
接着剤の役割は、前述したように物と物を接着する役割の他に、接着剤に粉末等を混ぜ固形の物質に成形したり、接着成分を薄め、様々なものに塗布し表面をコーティングしたりする役割などがあります。
以下で接着剤の構成成分と長所・短所、また、接着剤と粘着剤の違いは何なのかをご説明します。
接着剤の構成成分と長所・短所
接着剤には、様々な成分が含まれます。以下で順に見ていきましょう。
その成分において何が含まれるかは、主成分によって決まります。何をくっつけるか(被着材)、接着後どう使用するか、また、どんな性能が求められるかといった条件によって選定されます。 主成分は、主に高分子化合物でありますが、分類としては、有機系と無機系に分類することができ、有機系では合成系と半合成系、そして天然系に分かれ、さらに合成系は細かく樹脂系・ゴム系・複合系と分類されます。(表1参照)
溶剤とは、字の通り、溶かす役割のために添加されており、「ぬれ」を発生させるため接着剤の粘度を下げ、被着材の表面に均等に行き渡らせ、凹凸に入り込ませる役割を持ちます。主成分の高分子化合物に合わせ、溶剤が選択・使用されています。 主な溶剤として水が使用されますが、有機溶剤を使用して均一な分散性を持たせることもあります。
可塑剤という成分が接着剤に含まれている場合がありますが、可塑は「かそ」と読み「柔らかく変形させやすい」という意味です。つまり、可塑剤は主成分である樹脂やゴムに柔軟性を持たせる役割を持ちます。一般的には、ビニル樹脂系を主成分とする接着剤に使用されています。
主成分に粘着性が欠けている場合は、主成分と相性のよい粘着付与剤が添加されている場合があります。粘着付与剤として使用されるものには天然樹脂や石油系の合成樹脂などがあります。
主剤の補助的な役割を果たすもので、粘度の調整や増量目的で添加されています。また、接着層の強度や耐久力を向上させたり、多孔材に対しては滲み込みを防ぐことができます。
主成分が水性系接着剤である、エマルション(合成樹脂を水に乳化させた分散系溶液)であったり、ラテックス(天然ゴムや合成ゴムを水に乳化分散させたもの)の場合、粘度が低いため、水溶性高分子化合物である増粘剤が添加されています。
主成分の硬化が自然に行われない場合、硬化剤が添加されています。主成分と硬化剤が化学反応を起こし、硬化促進を行います。硬化剤は架橋剤と呼ばれることがありますが、それは接着成分を化学反応で結合させた際に網目状の構造を形成するためによるものです。
エポキシ樹脂系接着剤のように固形濃度が高い様な接着剤の場合は、希釈剤と呼ばれる液体を添加することで粘度を抑えることがあります。
接着剤が2液混合型の接着剤の場合は、混合する際の成分混合比率を確認しやすくするために顔料が用いられます。
その他にも主成分に合わせ、老・酸化防止剤、防腐・防カビ剤、消泡剤、難燃剤、香料などを接着剤の機能を補う添加物が添加されている場合があります。
| 有機系 | 合成系 | 樹脂系 | 熱硬化性 | ユリア系、フェノール系、エポキシ系 等 |
| 熱可塑性 | ポリ酢酸ビニル系、ポリビニル系、ポリビニルアルコール系 等 | |||
| ゴム系 | クロロプレンゴム系、ニトリルゴム系、シリコンゴム系 等 | |||
| 複合系 | ビニル・フェノリック、ニトリル・フェノリック 等 | |||
| 半合成系 | ニトロセルロース、酢酸セルロース、塩化ゴム 等 | |||
| 天然系 | にかわ、でんぷん、天然ゴム、カゼイン、松やに 等 | |||
| 無機系 | セラミック系、セメント系、ケイ酸ソーダ 等 | |||
接着剤の長所と短所
被着材の種類が異なる被着材同士を接合することもでき、被着材の形状に左右されることがなく、軽量で、仕上がりを美しくします。気密性と水密性があり、また接着剤の成分処方を変えることによって様々な機能を加えることが可能です。
一般的に、可燃性があったり、耐熱性や耐寒性が高くないものもございます。また、被着材により種類を選別する必要があり、適切な接着条件を守らないと、その性能を充分に発揮できません。 さらに、分離することは難しく、解体が非常に困難になります。溶剤を使用した接着剤(プラスチック用、ゴム系など)を使用する場合はでは有機溶剤中毒に陥る可能性がありますので、換気が必要です。
接着剤と粘着剤の違い
接着剤と粘着剤は、同じような働きをするため、明確な分類は難しく、接着剤の一部として粘着剤が分類されることもあります。今回はその粘着剤と接着剤の特長から違いを捉え、商品の選定に役立つ知識をご提供致します。
接着剤と比べた粘着剤の特徴
「粘着剤」は接着剤の一部として、感圧接着剤(英語では“Pressure-sensitive adhesive”)とも呼ばれています。粘着剤は常に濡れた状態を保っており、容易にくっつき、剥がすことも可能です。
JIS(日本工業規格)では、接着とは「同種または異種の固体の面と面を貼り合せて一体化した状態」(JIS Z 0109)と規定されており、一方、粘着とは「接着の一種で、特徴として水、溶剤、熱などを使用せず、常温で短時間、わずかな圧力を加えるだけで接着すること」(JIS Z 0109)とされています。つまり、粘着剤の大きな特徴として、固化しないことが挙げられます。接着剤はアンカー効果やファンデルワールス力、分子間力など様々な力で接着の力を発揮しており、共通して乾燥蒸発や化学反応により固体になりますが、粘着剤は上記の様に固体化しません。
粘着剤の特徴をまとめると、一般的に接着強度は接着剤より小さく耐熱接着性も低いですが、再剥離が可能です。さらに常温で接着でき、固化せずに強度を発現します。接合時の作業性は高く、ベースのポリマーはゴム系やアクリル系が多くなっています。

接着剤と粘着剤の違いとは?
接着剤と粘着剤は、剥離時の特徴に違いが見受けられます。接着剤の場合、剥離時に凝集破壊が起こります。凝集破壊とは、両側の被着材に接着剤が残った状態を言います。一方、粘着剤の場合は剥離時に凝集破壊が起らず、糊残りがない状態が理想的です。粘着の場合は凝集破壊は起こさず、接着はしっかりと起こすという、両極の性質をもつことが重要です。
粘着剤がこのように凝集破壊を起こさず剥がせるのは、粘着性の主流がアクリル樹脂やゴムであるためです。このアクリル樹脂やゴムの特徴として、流動性が挙げられます。特にアクリル酸ブチルはガラス転移(液体を過冷却したのちガラスに移り変わること)温度が低く、低温においても流動性に優れています。一方、アクリル板などのメタクリル酸メチルは硬く凝集力があるため、アクリル酸ブチルと共重合させて、それに粘着剤に含まれる成分をもって調整することで流動性と凝集力を得られるのです。
粘着テープと両面粘着テープ
粘着テープと両面粘着テープは、粘着テープが片側に接着を行うのに対し、両面粘着テープであれば、その名の通り両面に粘着を行う点でより接着剤としての機能が見られます。
両面粘着テープは感圧性タックにより通常の接着剤が状態の変化を有するに対し、貼り付ければ即座に実用的な接着効果を発揮し、容易に均一な厚さに塗布出来るため、作業性が大変高く、色々な場面に用いられています。
また、最近では、両面粘着テープを打抜き加工することで、通常では接着が困難なような場所に2次元的形状を持った接着剤として塗布することが可能となっています。

ホットメルト形粘着剤
ホットメルト形粘着剤では、ブロックポリマーと呼ばれるSIS(スチレンーイソブレンースチレン)やSEBS(スチレンーエチレンーブチレンースチレン)ゴム系をベースとし、SとIの部分にそれぞれ異なった粘着付与樹脂や軟化剤を使用することで、粘着剤を設計しています。
また、このスチレン系熱可塑性エラストラマーは海島構造からなっています。海島構造とは複数のプラスチック成分からなるポリマーアロイ(ポリマーの混合物)の様に成分同士のなじみが悪く混合しない2成分のうち、片一方の成分量が多い際に、表面部分に少ない方の成分が島のように点在している状態を指します。
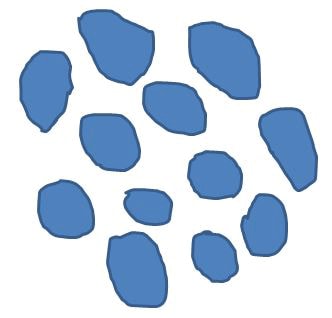
ガムテープは粘着剤?接着剤?
一般にガムテープと呼ばれる荷造り用粘着テープは、トーマス・エジソンによって発明され、粘着テープとされていますが、実は接着テープです。従来のガムテープは水溶性の糊が接着面の表面に塗布されており、切手と同じように水をつけ糊を最活性化させ接着力を発揮させていました。
現在のガムテープと呼ばれるものは水を使用しないものがほとんどですが、ガムテープと言う言葉が商標登録されていないため、梱包用のテープを総称してガムテープと呼ばれているのです。また、ガムテープより強力な粘着力を持つテープにダクトテープというのもあります。












